オリンパス 米谷氏のカメラ
2024年7月

左から、OLYMPUS PEN, OM-1N, XA
オリンパス(現在、カメラ事業はOMデジタルソリューションズに移管)は、戦前から続くその長い歴史の中で多くの個性あるカメラを生み出し、また写真の世界に変革をもたらしてきた。そして、そのオリンパス・カメラの興隆は、名設計者・米谷美久氏の功績なしに語ることはできない。米谷氏はその名声と存在感の高さゆえ、多くの賛辞とともに、独善的と評されることもあるようだが、それこそが、彼が今日に名カメラを多く残し、評価された理由であったとも言える。現に、それぞれのカメラを手にし、歴史を紐解くほどに、彼のその一貫した哲学と信念に驚嘆し同調せずにはいられない。
ここでは彼の代表作である3機種を題材に、そのカメラ哲学を紐解いていくことにしたい。
オリンパス・ペン (1959)

1956年に入社した米谷氏が2年間の工場実習を終え、設計部に配属されて最初に設計したカメラである。多忙な先輩社員から与えられた、半ば研修を兼ねた設計課題のようなところからスタートしたカメラだが、結果的には「ハーフ判ブーム」を巻き起こし、オリンパスを代表するカメラシリーズの端緒となった。
このカメラの魅力であり、また米谷氏がもっともこだわった点がレンズの画質である。当初の設計課題は、トイカメラ的なものなら簡単に設計できるだろう、というようなものであった。そもそも、目標とする販売価格が6,000円という極端な低価格であったため、全体のコストのバランスから言えば、よくてトリプレットクラスの低廉なレンズがついてしかるべきカメラである。そこに彼は当時、高性能で知られたテッサー型のレンズを搭載することにこだわった(*1)。オリンパスのレンズ設計部門の高い技術力もあり、実写結果でも、また客観的な測定結果でも極めて高い性能を示すレンズが、この破格に安価なカメラに搭載されることになった。

オリンパス・ペン(初代)での作例
このペンでの撮影例は、現代の高性能レンズの描写を見慣れた目にも依然、先鋭に映る。滝の流れを滑らかに描写するため、より絞り込んで長時間露出したものもあったが、絞り込むとかえって回折で鮮鋭度が低下したため、敢えて絞り込んでいないときの作例を挙げた。カメラやレンズの性能を厳格に評価していたことで知られるアサヒカメラの名記事「ニューフェース診断室」でも、絞り開放から画面全体の至るところで解像度が100本/mmを切ることがないとされ、これは他のハーフ判カメラに比べても優秀な結果である。画面サイズが小さいため、そもそもこのレンズの性能を引き出すにはフィルム性能はもちろんのこと、その後の現像等の作業にも高いレベルが求められ、易々とその実力を評価することはできない。なおペンはシャッターがレンズ全体の後ろに置かれた、いわゆるビハインド・シャッター型だが、絞りはそれとは別に、レンズ前群と後群の間に設けられている。小さなレンズであるため、シャッターがない分だけ前群と後群の間の距離を詰められる利点があるものと思われる。
問題は、なぜそこまでレンズにこだわったのか?という点である。米谷氏はオリンパス入社前からカメラ・写真に造詣が深く、ライカを愛用していたことで知られる。このこだわりは、彼自身が「ライカよりも気楽に持ち歩ける小型軽量ボディで、しかし写りに妥協しないカメラが欲しい」という思いを貫いた結果だというのだ。確かに、これはいかにも「独善」である。しかし一方で、この「独善」がペンの名声の原動力となり、カメラ業界の勢力図まで変化させることになったのである。「安かろう悪かろう」では、とうてい、ハーフブームは起こらなかったと思われるのだ(*1)。

それでは、そのレンズにかけられたコストのしわ寄せを食ったところはどこか。その1つが、この巻き上げ方法だと言われる。当時のカメラ業界では、レバー巻き上げがカメラの商品力として重要な要素とみなされていた。レバー巻き上げは1951年のレチナIIaが先鞭をつけ、1954年のライカM3やニコンS2で決定的となった、当時ホットな方法であり、カメラの商品力のためには、すぐにはわかりにくいレンズ性能よりもレバー巻き上げの搭載が優先されてもおかしくない時代である。そこを敢えて割り切り、上の写真のようにスプロケットギアに径の大きなノブを直結し、一部を背面から露出させる方式でコストを徹底的に切り詰めた。これだと、レバー式と同様にカメラをホールドしたまま巻き上げが可能であり、ノブの径も大きいので要する力も小さくなる。普通の持ち方では一度の巻き上げに2回ほどの動作が必要であるが、指の付け根から先に向かって滑らせるようにすれば、1回の動作で巻き上げを完了させることもできる。
この方法は、部品点数が多く調整や検査の手間もかかるラチェット機構(爪)に頼らないフィルムカウンターメカニズムとあわせ、オリンパスペンの低価格を実現した立役者であるが、実際に使ってみると、極めて軽く、小気味よく巻き上げることができ、なんの不都合もない。フィルムの巻き上げ量が小さいハーフ判カメラであるということと相まって、歯車やラチェット機構がないことは、抵抗を減らすことにも寄与しているのだ。


このフィルム巻き上げ方式は、今見るとなんでもない、当たり前の方式のように見える。レンズ付きフィルムでも多く採用されている方式だし、上の写真のように後のXAにも採用されている。しかし、当時のカメラのフィルム巻き上げはレバー式のほか、バルナック型ライカ等に見られるカメラ上面のノブ式が主流で、ペン登場時、この方式は新方式と言ってよいものだった。ペンの場合、ノブがカメラ内側に寄っていることも特徴的である。これはスプロケット直結というメカニズムの都合もあるが、実際に使ってみると、カメラをホールドしたまま巻き上げやすい位置であり都合がよい。ただし、かわりにファインダがレンズ真上からずれた位置にある(カメラ前面から見ると、レンズ真上の特等席がブライトフレームの採光窓となっている。光学的には逆の配置にすることが可能だが、そうなっていないのは、この指との干渉を避けたためだと思われる)。これも、ライカ使いの米谷氏からしてみれば、さしたる問題でないことを知っていたからに違いない。

もう1つのペンのこだわりが、その薄さである。カメラ自体の厚みは、さほど他のカメラと変わらない。パトローネの太さにより厚みが決まってしまうためである。しかし特筆すべきは、そのレンズの突出の小ささである。これこそが、ハーフ判カメラという方向性にたどり着いたキーの1つと言われている(*2)。画面が小さいほど、レンズの焦点距離が短くなり、結果的にカメラが薄くなるのである。しかしレンズの周囲には、シャッター速度、距離(ピント)、絞り値の3つの値を調整するリングを備えなければならない。これをもし前後に順に配置すると、とてもこの厚みにはできない。そこで、ピントリングの内側を一旦凹ませ、そこに絞り値の指標と絞りリングを配置することで、厚みを増やさず、かつ、絞りを操作しやすくしてある。つまり、見るからに薄さを意識した設計となっているのである。
この設計にもやはりライカ使いの影響が見て取れる。当時のエルマーレンズは絞り値をレンズ前面で操作、確認するように作られている。かなりせせこましい、特異な操作方法だが、使ってみるとこれで必要十分である。ペンは、それを参考にしながらも、ずっと操作しやすく作られている。フォーカシングにより絞りリングに手が触れて絞り値が勝手に変わることもない。極めて優れた設計である。
ただし、米谷氏自身も「思ったほどにはカメラを小さくできなかった」と述懐している(*3)。それは当時のシャッターの寸法のためである。ペンではシャッターがボディの奥深くに沈んでいるため、左右にフィルム室を確保し、その間にシャッターメカニズムを挟んだ時点で小型化には限界が生じるのである(さきの内部写真では、画面とパトローネ室の間に無駄なスペースがあるように見えるが、これはシャッターを収めるために不可欠なスペースである。反対側は、スプロケットの奥にシャッターが収まっている)。

ペンは目測カメラだが、フォーカスリングには0.6mまで刻まれており、実際にはそれより更に少し近く、約55cmぐらいまでピントを合わせることができる(さらに簡単な改造で回転角を増やすことができ、その場合は約45cmまで近接できる。上の写真はそのような改造をした個体の最短撮影距離時であり、∞のすぐ近くまでほぼ1周、フォーカスリングが回転することがわかる)。後のカメラではピクトグラムを用いたゾーンフォーカス式になっているものも多いが、初代のペンはゆったりと回転するフォーカスリングで物理的な距離値をセットし、精密にピント合わせすることができる。このあたりも、敢えて初心者に媚びすぎず、手練れにとって使いごなし甲斐のあるカメラにしたい・・という米谷氏の考えが見え隠れする部分である。
乾板やシートフィルム等の大判カメラから、中判のロールフィルムへ、そして35mmへと、カメラの歴史は画面サイズの小型化の歴史でもあった。実際、当時はさらに小さい16mmカメラやミノックスがあり、その後もポケットインスタ(110フィルム)やAPSなど数多くの提案があった。しかし、ハーフ判カメラブームは、1960年代の終わりごろには終焉に向かう。その原因の1つはカラーフィルムの性能とも言われるが、もっとも大きな影響があったのは米国コダックの政策であろう。コダックとそのDPEネットワークがハーフ判を拒絶したために米国ではハーフ判カメラが全く普及せず、それが結果としてハーフ判の息の根を止めた。ここを乗り越えていれば、もしかしたら写真の世界は少し違っていたかもしれず、そうだとすると、ペンと米谷美久は、ライカとオスカー・バルナックのように言われていたかもしれない。もっとも、他の小フォーマットカメラも、ことごとく絶滅するのであるが。
OM-1 (1972)

OM-1 はオリンパスが満を持して発売した旗艦(フラッグシップ)カメラであり、数多くのアクセサリとともに発売されたシステムカメラであった。顕微鏡も製造するオリンパスらしく、「宇宙からバクテリアまで」というキャッチフレーズも有名である。しかし、その実、このカメラの最大の特徴は小型化であった。そしてここにも、米谷氏の哲学と思想が色濃く反映されている。
例によっていくらか先行例があるものの、やはり一眼レフカメラ主軸化の流れは1959年発売のニコンFが決定づけたと言ってよい。ニコンFは多様なアクセサリや拡張性、そしてなによりその頑健性からあらゆる分野に普及したが、最大の欠点があった。それは、その重さ、大きさである。シャッターメカニズムがほぼ同一であるニコンSPが幅136mm 高さ81mm、重さ590gであったのに対し、ニコンFはそれぞれ147mm, 98mm, 685g と大きく重くなっていた。それは、クイックリターンミラーやプリズムのためである。この、誰もが諦めていた欠点を解決するため、小型化を追求しながらも、フラッグシップとして遜色ないカメラを目指して設計されたのがオリンパスOM−1(登場当初はM-1)であり、当時、世界最小最軽量であった。
正直なところ、この戦略が市場にどれだけ受け入れられたのかについては、疑問も残る。ニコンFがあまりに頑丈であったため、フラッグシップといえば大きく重いがそのぶん頑丈な、いかにもプロの道具・・という価値観が行き渡ってしまい、それは、現在のプロ向けデジタルカメラにもなお残るように思えるからだ。その意味で、やはりこの小型化戦略は、米谷氏の独善であったと言うこともできるだろう。ただし一方で、一眼レフカメラ最後発組であり、それまではペンや35シリーズなどもっぱら入門向けカメラしか作ってこなかったオリンパスとしては、正面からぶつかる大艦巨砲主義的なカメラを発売したとて、対抗できたとは思えない。なにより、あのキヤノンが、手を変え品を変えながら挑戦し、前年の1971年にはキヤノンF-1を発売するも、とうとうAF時代になるまでニコンからトップを奪うことがなかったフラッグシップカメラ市場である。ニコンも同じく1971年にF2を発売する中で、とても正面からぶつかる事ができる状況ではなかった。実際、ミノルタも1973年にX-1で正面から対抗するも、一定の存在感を示すには至らなかった。

左から、ライカIIIc, オリンパス OM-1N, ニコンFG。全て50mm F1.4レンズを装着
そして、このOM-1は、小型化を追求した結果、ライカと同じ横幅となった。しかも、M3等よりも小さな、バルナック型だ。なにも、ライカと同じであれば合格というルールがあるわけではない。米谷氏も、ライカを基準にしたわけではなく、小型化を追求した結果が136mmになったという(*4)。いずれにしても、ミラーボックスのある一眼レフカメラで、ライカ同様の布幕横走りシャッターを用いて同じ横幅を実現するのは、相当な困難を伴ったに違いない。しかも、ニコンF/F2とは異なり、露出計が組み込まれている。さすがに重さは510gと、ライカIIIfより100g重くなっているが、これも一眼レフとしてはたいへん軽量である。

左から、ライカIIIc, オリンパス OM-1N, ニコンFG。全て50mm F1.4レンズを装着
小型化にこだわったのは、幅だけではない。さすがにペンタプリズム部分は突出するが、肩の部分は、バルナックライカの距離計の上面よりも低い。さらに、ペンタプリズムの底部を曲面にして、ペンタプリズムとフォーカシングスクリーンの間のコンデンサレンズをなくすことで高さを抑える工夫も施されている。
OM-1 はその後の一眼レフに大きな影響を与えた。例えばニコンでは、OM-1登場当時はニコマートシリーズが発売されていたが、大きく重いものであった。しかしその後、ニコマートがFM/FEシリーズに交代したときに小型化され、さらに入門機のEM/FGシリーズが1979年から順次発売されることで、ようやくOM-1とほぼ同じ横幅となった。上の写真では大きさがよく似ており、マニュアル露出が可能になったニコンFGを並べているが、これは1982年発売で、OM-1の10年後のカメラである。重量は490g と、樹脂を多く用いながらも20gしか変わらない。

OM-1の小型化とフラッグシップ性の両立が端的に現れているのが、この裏蓋を開いたときの様子である。カメラの高さを低くするため、前述のようにプリズムの形状に工夫を加えることでプリズムを低く設置してあり、それに伴い、ファインダのアイピースもギリギリの高さまで下げられている。しかし、ファインダのスペックは高く、大きなアイピースからもわかるように大変覗きやすいものとなっている。アイピースが丸型でないのは、この大きさと低さを両立させるためである。
なおニコンFGも高さの抑制には努力が払われており、二重遮光式シャッター(露光後、先幕がすぐに戻り、先幕と後幕の両方が閉まった状態により完全な遮光を実現する)により、シャッター後幕の格納部分のスペースを極限まで削減してある。ファインダのアイピースと画面との間に後幕が重なって収まるため、ここの距離を小さくするためには、羽根をより多く分割するとともに、羽根同士の重なりを抑える必要がある。そうすると漏光の危険が生じるため、二重遮光方式が開発された。シャッターメーカのセイコーがこのような複雑な技術に挑戦したのも、OM-1の驚異的な低さが影響したものとも言える。ペンタプリズムの突出はいつでも「必要悪」なのである。


OM-1はフラッグシップカメラであり、システムカメラなので、モータードライブも装着できる。当初のOM-1は改造が必要であったが、このOM-1Nは無改造で装着できるようになった。円形の蓋のうち、小さい方を開けるとモータードライブのカップリングが現れる(大きい方は電池室である)。一方、当時のフラッグシップカメラを象徴する、交換式ファインダはOM-1では採用されていない。
XA (1979)

左から、XA, XA2
オリンパスXAはケースレスカメラである。カメラそのものがケースである、といっても良い。スライド式のバリアを閉じると、レンズだけでなく、ファインダも、対物窓、接眼窓ともに隠れてしまう。XAに至っては、距離計用の窓までシャッターで閉じられる。
このカメラにも、米谷氏の思想が色濃く反映されている。彼自身が様々な場で述べているように、どんな出来事が起こっても、その場にカメラがなければ撮影できない。スマートフォンが普及した今でこそ、世界は映像にあふれているが、当時は「撮り逃がされる」ことが普通であった。なので、カメラはできるだけ小さくなければならない。これは、前述のペンやOM-1でも追求されてきたことである。また、自動露出によりカメラの操作も相当に自動化、簡単化された。しかし、XAシリーズではそれらよりも根源的な問題、すなわち「ケースから出す」「キャップを外す」「電源を入れる」などの作業をなくし、徹底的にシャッターチャンスに強いカメラとしたことが大きな飛躍であった。

バリアを開けたところ
XAシリーズでは、最初に出た高級タイプのXAが、距離計連動型(レンジファインダー)であるために人気がある。しかし、前述した「シャッターチャンスへの強さ」に関しては、XA2をはじめとする廉価モデルの右に出るものはない。なにしろ、バリアを開けばあとはシャッターを押すだけなのである。向かって左側の、ゾーンフォーカスレバーを動かすことで距離合わせが可能であるが、バリアを閉じるとパンフォーカスの位置(人が二人の、オレンジ色の位置)に自動的にレバーが戻るのが、その特徴を際立たせている。また、露出も完全に自動(プログラムAE)なので、絞り設定の余地もなく、ユーザは本当にシャッターを切るだけ、なのである。つまり、ケースレスカメラの精神にもっとも忠実なのは、XA以外のXAシリーズであると言える。しかしそれで話が終わらないのが、このシリーズの名声を高めているのもまた事実だ。
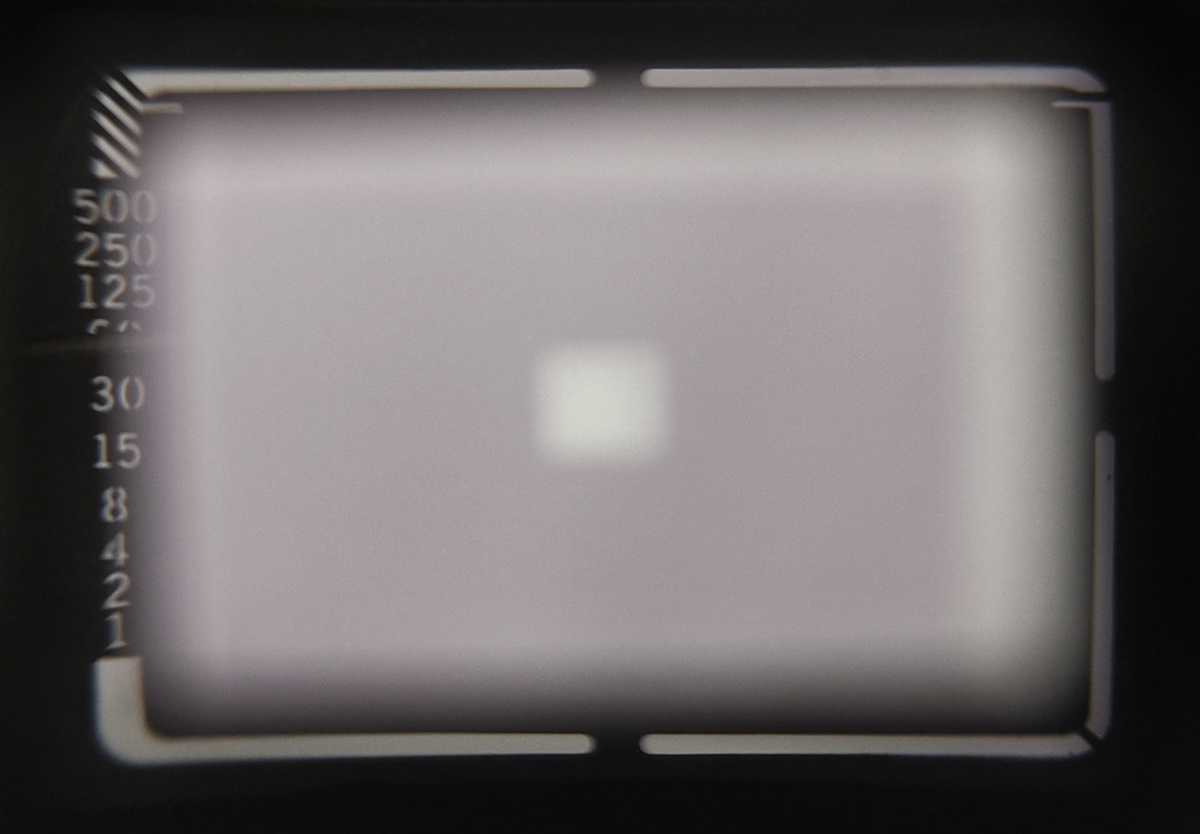
XAシリーズでは、XA2が特に大量に売れた。それに比べると、高級モデルのXAは複雑でコストもかかっており、ビジネス的には「なくても良いカメラ」だったのではないかとも思われる。価格も、27,800円に対して32,800円と、5,000円しか違わないのだ。しかし、それでもこのXAが存在するところにまた、米谷氏の影響を感じずにはおられない。やはり、ある程度写真にこだわると、きちんと被写体にピントを合わせたい、絞りで被写界深度をコントロールしたい、という衝動には抗いがたい。しかし、XA登場時には、距離計連動型カメラは既に衰退の途上にあった。特に、コニカが1977年にC35AF(ジャスピンコニカ)を登場させ、一気にオートフォーカス化の機運が高まっていた時期である。どのカメラメーカも、対抗すべくAF機の開発を最優先で進めていたはずだ。しかしその時期に、敢えて距離計連動型、絞り優先AEのカメラを出したという事実は、やはりある種の、立場ある方の「わがまま」を感じずにはいられない。そして、そのわがままが、今の我々にとっていかにありがたいことか。オートフォーカスと言えど、意図したところにピントを精密に合わせることはできないのだ。もっとも、オリンパスもオートフォーカスカメラ (C-AF) をXAの2年後の1981年に発売しており、両面作戦であったことは疑いようのない事実である。
オリンパスXAの登場のきっかけの1つに、小型化を追求した35mmフルサイズカメラ、ローライ35の登場があると言われる。オリンパスが拓いたハーフ判カメラと同等の大きさでフルサイズ化を達成したことは素晴らしいが、ケースやキャップを要し、マニュアル露出、沈胴式でチャンスに弱いことや、厳密な距離合わせができないことがやはり難点に映ったのだろう。また、樹脂製の小型軽量コンパクトカメラとしては他にもリコーFF-1(1978), コシナCX-2 (1980), チノンベラミ (1981), ミノックス35 (1984) などが前後して発売されたが、これらはすべて目測式のカメラであった。同等の大きさ重さで距離計を搭載したカメラはおそらく、コンタックスT (1984)と、XAを参考に開発したと思われるベラルーシ製のBelOMO Elikon-1 (1985)のみである。
沈胴式でなく、カメラそのものが薄い・・ということの良さ(*5)は、オリンパスペンと相通じるところでもある。惜しむらくは、このXAの続編が続いて欲しかったことであるが、ビジネスを営む企業にそれを望むのも酷というものである。そのような中で、自らの哲学を貫き通し、発売までこぎつける米谷氏とオリンパス開発陣の力。また、それを評価し応える市場との間のコミュニケーションは、カメラ史の中の光であった。
XAシリーズの詳細についてはこちらもあわせて参照されたい。
参考文献
- カメラ設計残酷物語 : カメラレビュー クラシックカメラ専科 No.48 から連載。
- 「オリンパス・ペン」の挑戦 (クラシックカメラ選書 26)「カメラ設計残酷物語」の前半に対応。
- 一眼レフ戦争とOMの挑戦: オリンパスカメラ開発物語 (クラシックカメラ選書 33)」「カメラ設計残酷物語」の中盤〜に対応。
脚注
- *1 : 「カメラ設計残酷物語 (3) 「オリンパス・ペン」の設計」に、カメラのコンセプトから、レンズ設計者には「3枚玉のトリプレットタイプで、前玉回転で行こう」と言われたこと、それに対して「F3.5, 4枚構成のテッサータイプで最高のレンズがほしいのです。それを全体繰り出しで行きます」と言ったとある。また、「このレンズへのこだわりこそが、その後の「オリンパス・ペン」の人気を支えた大きなキーポイントの1つだったことは疑うべくもない。」と記載されている。
- *2 : 「カメラ設計残酷物語 (2) 「オリンパス・ペン」の設計コンセプト」に、上司との会話が紹介されている。上司の「いつもポケットに入れて持ち歩けるカメラが欲しいなあ」「レンズが出っ張っていて邪魔なんだよね」という発言から、「いっそのこと、画面を半分に切ってみるか。シネサイズにするとレンズも短くなるし・・・」と、話が具体的になっていく様子が紹介されている。なお同記事の末尾に、画面サイズが小さくなると被写界深度が深くなり、ピンボケが出にくくなることが「ハーフサイズを採用したもう一つの理由」とも記載されている。
- *3 : 「カメラ設計残酷物語 (3) 「オリンパス・ペン」の設計」に、図入りで解説されている。
- *4 : 「カメラ設計残酷物語 (18) 「M-1」のレイアウト」で、「偶然、ライカIIIfと同じになっていたのだが指摘されるまで気が付かなかった。」と述べている。
- *5 : 「カメラ設計残酷物語 (30) 「プラスチック化とデザイン」で、ライカの沈胴式レンズについて「撮影のたびにレンズを出したり入れたりしなければならないので操作が面倒である」と述べている。